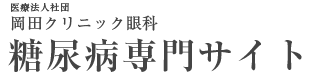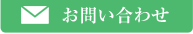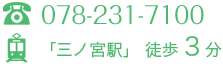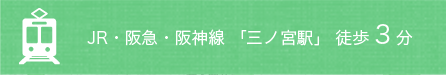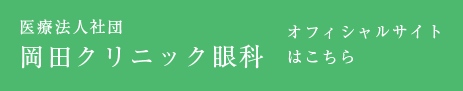糖尿病とは

糖尿病には自己免疫異常などの関与が考えられる1型糖尿病と遺伝や生活習慣などが原因で発症する2型糖尿病があり、本サイトの糖尿病は主に2型糖尿病のことを意味します。
2型糖尿病(糖尿病)は血液中のブドウ糖(血糖)が正常よりも多くなる病気です。
初期の頃は自覚症状がほとんどありませんが、血糖値を高いまま放置すると、徐々に全身の血管や神経が障害され、いろいろな合併症を引き起こします。
糖尿病の原因には遺伝と高カロリー、高脂肪食、運動不足などにより引き起こされる「インスリンの作用不足」などが考えられます。
インスリンは、膵臓のランゲルハンス島のβ細胞でつくられるホルモンで、血糖値を下げる働きがあります。
糖尿病では「インスリンの作用不足」を改善し、血糖値を上手にコントロールすることが大切です。
そうすることで、病気の進行を防ぎ、合併症を予防することができます。
糖尿病の原因と症状
糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの働きの低下、つまり「インスリンの作用不足」が原因で起こります。 糖分を含む食べ物は唾液や消化酵素でブドウ糖に分解され、小腸から血液中に吸収されます。 食事によって血液中のブドウ糖が増えると、膵臓からインスリンが分泌され、ブドウ糖が筋肉などに送り込まれエネルギーとして利用されます。 そのため「インスリンの作用不足」が起こると、血液中のブドウ糖を上手に処理できなくなり、血糖値の高い状態が続くようになります。
なぜ「インスリンの作用不足」がおこるのか
「インスリンの作用不足」には2つの原因があります。 1つは、膵臓の働きが弱くなりインスリンの分泌量が低下するため(インスリン分泌低下)、もう1つは肝臓や筋肉などの組織がインスリンの働きに対して鈍感になり、インスリンがある程度分泌されているのに効きにくくなるため(インスリン抵抗性の発現)です。 糖尿病では体質以外にも、肥満や運動不足や食べ過ぎといった生活習慣の乱れが、「インスリン分泌低下」や「インスリン抵抗性の発現」を引き起こすと考えられています 。
このような症状の方はお気軽にご相談ください。
- のどの渇き
- 尿の量、回数が多い
- 体重が急激に減った
- 全身がだるく、疲れやすい
- 目がかすむ(視力障害)
- 尿に糖が出る
のどが渇き、尿の量・回数が増えるのは、大量のブドウ糖を排出するため尿の量が増えてしまい、体の水分が失われてのどが渇くため。
食べているのにやせるのは、食べてもブドウ糖が正常に利用されずに、慢性的なエネルギー不足になるため。
全身がだるく、疲れやすくなるのは、インスリンの作用不足でブドウ糖を利用できず、活動エネルギーが足りないため。
上記以外にも足や手の指などに「しびれ」や「ぴりぴりした痛み」「ジンジン、チクチク」したりと違和感などある場合には早めに医師に相談しましょう。